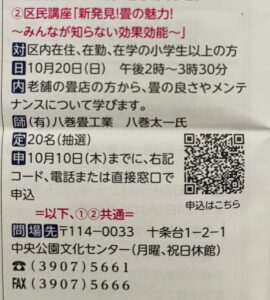一昔前と違い和室の洋風化が加速している昨今【畳】について存在は知っていても、どういった素材でどのような機能があり、価格の差は何なのか?ということを知らない方が増えています。
「増えています」と言うより「畳のことなんか知らなくて当たり前」になっていますよね。
自宅に畳が無い状態で育った若い子は勿論ですが、建築に携わる設計士や建築士の方も実は畳のことをほとんど理解していません。
そのような状況が続くことにより、ますます畳離れと言いますか、日本固有の和文化が消滅危機にあります。
私は畳屋になった約30年前より、このような世の中になることは予測できていましたので、微力ですが近所の小学校の町探検に協力し子供の頃から畳に慣れ親しんでもらう努力をしてきました。
現在では畳業界のメーカー・商社・畳店などで出来た【畳でおもてなしプロジェクト】という団体に加盟し、また同じ和文化であるお茶(茶道)・お花(華道)・着物業界と連携し【和文化・産業連携振興協議会】としても活動の輪を広げております。
今年の夏も多くのイベントをお手伝いし、畳の魅力を一般の方や建築士の方に発信してきました。
畳でおもてなしプロジェクトはこちら↓
和文化・産業連携振興協議会はこちら↓
7/10 訪日観光客の和文化体験
畳でおもてなしプロジェクトでは茶道業界と連携して訪日外国人の方に、ミニ畳作りと茶道を体験していただきました。
この日、私は参加できなかったためレポートを貼り付けておきます。
言葉の壁はありますが皆さん楽しんでいただけたようで何よりです。
7/14 全国女性建築士連絡協議会・東京大会
コロナ禍以前から行っているイベントで、2年に一回東京の建築士会館にて『全国女性建築士連絡協議会・東京大会』が開催され、それに合わせて会場の一角にてミニ畳作りを体験してもらっています。
東京大会の翌年は必ず地方での開催になり、そちらにも出展していますので毎年やっている感じですね。
この場ではミニ畳を作ってお持ち帰りいただくだけではなく、畳の素材や機能性についても一人一人に解説し、新築の設計では一部屋でも多く畳を採用してもらうために努力しました。
普通に『畳表(たたみおもて)』と言っても種類が豊富にあることをご存じでしたでしょうか?
天然藺草(いぐさ)にも品種や品質による等級や価格差があり、床の間には龍鬢表(りゅうびんおもて)という新品の状態なのに日焼けした目幅の広い畳表が使用されます。
琉球畳は大分県国東市で栽培され、七島藺(しちとうい)というカヤツリ草科の植物を縦半分に割いて織り込んであり、この畳表を使用した畳のことを縁が付いていても付いていなくても【琉球畳】と呼びます。
沖縄で栽培される藺草で作った畳表は琉球畳ではなくビーグという太い藺草が原料になり【ビーグ表】と呼ばれます。
ややこしいですね。
他にも樹脂製や和紙製、塩ビ製の畳表もあります。
畳の芯材である『畳床(たたみどこ)』にも種類が多くあり、藁(わら)製はもちろんですがダイケンボードや、転倒などで怪我をしにくい衝撃緩衝床という商品まであります。
畳の縁も1000以上あると言われていますし、好きな柄を選んでオリジナルのミニ畳を作成するこのイベントは、女性建築士の方々に大変好評でした。

多種多様な素材を並べてご説明

ミニ畳作成する女性建築士の方
7/26~27 夏のわくわくキッズフェスin日本橋2024
三井タワー・アトリウムにて和文化・産業連携振興協議会の四団体によるワークショップを行いました。
体験は主に小学生のいるご家族で子供と保護者の方が一緒に楽しんでいただきました。
お茶業界は『冷茶の淹れ方体験』を、着物業界は『染め体験』をし、畳とお花業界はコラボして『ミニ畳の上に水中花体験』をしていただきました。
我々のブースではまず好きな色柄の畳表と縁を選んでいただきミニ畳を制作します。
完成したら好きなお花や植物を選んで水中花を作り、畳の上に乗せて記念撮影を。
当初スタッフが多く集まったので余裕かと思いきや、大変好評で忙しく働かせてもらいました。

まず材料をえらんでもらい

ミニ畳の作成

生花の家元自ら指南して

完成品がこちら
8/2~4 ものづくり匠の技の祭典2024
このイベントは毎年東京都が主宰している技能士が集まって来場者に職業体験してもらう企画です。
私が所属する『東京都畳工業協同組合』として出店し、ミニ畳を制作したり畳の小物を販売したりしました。
来場者は子供とその保護者が多いのですが、大人は圧倒的に天然藺草の畳表を選ぶ方が多いですね。
藺草の香りにはバニリンやフィトンチッドと呼ばれる癒し成分が入っており、この香りを楽しみたい方が天然藺草の畳表をチョイスしています。
もう一つの畳表はダイケンの和紙表で、こちらは日焼けせず樹脂加工してあるので水も弾く仕様になっています。
カラーも選べるので子供たちからは人気です。

畳組合のブース
8/7~8 農水省こども霞が関デー
コロナ禍以前にもお手伝いしていましたが、久々の夏休み親子体験会が農水省内で行われました。
この日は一般に農水省を開放し、事前予約制が多いのですが各ブースに子供たちが学んで体験できるコーナーがたくさんありました。
私のブースでは絹の原料である蚕コーナーと、同じ茶葉で違う味を飲み比べるコーナーがあり、それぞれ畳の上で体験していただくことができました。
このイベントは業界団体ではなく当店に依頼が来ましたので、従業員と二人で子供と保護者の方に畳の機能性や良い所の説明を。
その後で千代紙を縁にした畳コースター作り体験をしてもらいました。
途中、くまモンが来てクイズコーナーをしてくれたお陰で、ゆっくり休むことができました。

畳敷きのブース

靴を揃えて上がる子供達

国会議員の先生も参加
畳のイベント開催にご興味のある方は
時季や費用、規模によって異なりますが、畳の魅力を伝える活動は今後も続きます。
多くの方に畳の良い機能や素材による性質を知ってもらうため、このようなイベントにご興味のある方はお知らせください。
打ち合わせや材料の手配もございますので、ご連絡は早めにお願いいたします。