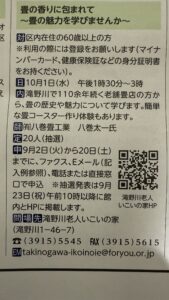皆さま、こんにちは。
(有)八巻畳工業の四代目です。
今年も琉球畳の命とも言える「七島藺(しちとうい)」の刈り取りに、大分県国東市まで行ってきました。

今回で4回目の現地訪問ですが東京から飛行機で片道約1時間半、現地での刈り取り作業は3日間に及びました。
この活動は、単なる農作業の手伝いではありません。
琉球畳という日本文化を未来に残すための、私たち畳職人の使命と私は考えています。
過去の刈り取り体験についてはこちらの記事もご覧ください。

鎌を研いで

長さを揃えて切ります

七島藺の断面は三角形
1.七島藺の希少性と現状
七島藺の現状を正確にお伝えすると畳表として流通する七島藺農家は、大分県国東市にわずか3軒しかありません。
中国産の七島藺もほぼ廃業しており、全国的に入手が極めて困難な状況です。
年間流通量は畳表に換算して約900畳分。
市場に出回る量としては極端に少なく、流通の希少性が琉球畳の価値を高めています。
さらに農家さんは高齢化も進んでおり人手不足にもかかわらず、畳屋さんはほぼ現地に足を運ばず、刈り取りの手伝いも行いません。
そのため私は毎年声を掛け合い、本気の仲間とともに現地に赴いて刈り取りを行っています。
この活動を継続する理由は単に良質な畳表を手に入れるためだけではありません。
琉球畳という日本文化を未来に残すための責任として取り組んでいるのです。

根本は円形で太さがバラバラ

右の細い七島藺は裂かずに工芸品に
2.現地での刈り取り作業
刈り取りの工程自体は過去の記事とほぼ同じですが、今年はさらに詳細をお伝えします。
草丈が十分に成長した七島藺を確認し網を外す
手鎌で丁寧に刈り取り
刈り取った藺草を三角形の断面に沿って分割
乾燥窯で乾燥
デリケートな「はかま取り」を丁寧に行う
袋詰めして保管
七島藺の茎は三角形の断面をしており、縦方向に分割することで製織しやすくします。
この作業や藺草の根本にある「はかま」や先端にある葉を取り除く作業は、非常にデリケートで神経を使います。
熊本県で栽培される藺草(いぐさ)と比べても強度が弱く折れやすいため、手早く、かつ丁寧に作業する必要があります。
農家さんの作業は明け方から日没までですが、私たちは朝7時から夕方18時までと時間を制限してもらい、あまりの暑さには昼休憩も長めにとっていただきながら作業を行いました。
集中力を要求される作業ですが、農家さんから直接「助かった!」と感謝される瞬間は、何ものにも代え難い喜びです。
刈り取った七島藺は乾燥後に袋詰めされ、農家さんが「半自動織機」を使って1日に1畳ずつ製織していきます。
農繁期には製織作業ができないため、年間で7〜8ヶ月しか生産できません。
このため刈取りを手伝っている私でさえ、時期によっては入荷に半年から1年待つこともあります。


短い草を抜く選別作業

分割機で縦半分に割く

半分になった七島藺
3.七島藺農家の思いと価格の現実
琉球畳の価格は年々高騰しています。
しかし農家さんの利益は決して十分ではありません。
手間と時間をかけて育てた畳表を出荷しても、生活が豊かになるほどの収入は得られません。
それでも農家さんは「日本の文化を守るために」という強い意志で作業を続けています。
私が現地で刈り取りを手伝う理由は単なる仕入れではなく、農家さんを支え、琉球畳文化を守ることにあります。
この文化を未来に伝えるために、汗を流し、現場で学び、協力することは私の使命であり喜びでもある。と言ったら大袈裟ですかね。

4.七島藺で作る琉球畳の特性と魅力
琉球畳は縁がない畳を指すことが多いですが、七島藺を使用して作られた畳は、縁があってもなくても「琉球畳」と呼ばれます。
過去の記事でも触れた通り、琉球畳の特性は以下の通りです。
耐久性:七島藺は丈夫で使用頻度の高い場所でも長持ちします。
天然素材ならではの弾力と香り:裸足で歩くと心地よい弾力があり、牧草のような香りにはリラックス効果があります。
メンテナンス性:天然素材ですが、ほこりや湿気を調整する機能を持つため、室内環境を整える助けにもなります。
琉球畳は単なる床材ではなく日本文化の象徴であり、国産七島藺を使用することで、他では味わえない品質と価値を持っています。

珍しい天日干し作業

叩いて袴を落とす作業
刈り取り体験の重要性
過去の記事でも述べたように、私たち職人が現地に赴き、刈り取りを体験することには大きな意味があります。
・農家さんの負担を軽減し品質を守る
・七島藺の希少性と栽培の苦労を理解する
・消費者に正確な情報と価値を伝える
この体験があるからこそ、私たちはお客様に「本物の琉球畳」を安心しておすすめできるのです。

折れやすいので大事に受け取ります
まとめ
・畳表として流通する七島藺農家はわずか3軒、年間約900畳分しか市場に出回らない希少素材
・中国産も廃業し、琉球畳は絶滅の危機にある
・農家さんは利益が少ないにも関わらず、日本文化を守るために尽力している
・刈り取りは暑さや湿度の中での重労働であり、三角形断面の分割や、はかま取りなど非常にデリケート
・乾燥窯の温度調整、半自動織機での製織、年間7〜8ヶ月の生産制限がある
・熊本県産藺草よりもデリケートで神経を使う作業である
・琉球畳は縁がある・なしに関わらず、七島藺使用で高い耐久性と快適性を備え、文化的価値も高い
・刈り取りから製織までの工程を知ることで、琉球畳の価値をより深く理解できる
・(有)八巻畳工業では、こうした現場経験を基にお客様に本物の品質を届けることを使命としている
七島藺の琉球畳は、こだわりのあるお客様にとっては単なる床材以上の価値があります。
手間暇かけて育てられた藺草、慎重に刈り取られ、分割・はかま取りされた後に織り上げられる畳表は、まさに職人と農家さんの技術と想いの結晶です。
この貴重な七島藺を使用した琉球畳を、私たちは東京の皆さまのご自宅にお届けしています。
琉球畳に関するお問い合わせ
琉球畳のご相談・お見積もりはとても簡単です。
QRコードを読み取り、ライン公式からお問い合わせください。